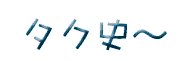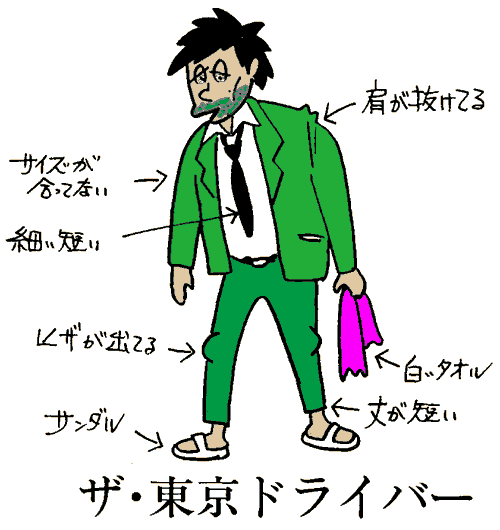| |
|
| |
口上
|
歴史フリークの私め、青空遊歩がナント、日本のタクシー史を記します。
とはいえ、明治から昭和までは拾い集めた資料を私めの解釈にして転載します。
平成時代からはこの目で見た聞いた出来事をまとめて行きますが、明治から昭和までは拾い集めた資料の転載でお許し下さい。
※只今休筆中です。
その間、歴史ドキュメントがありました。
タクシー百年です。
|
タクシー百年祭
8月5日 有楽町駅前でした
|
暑い中、関係者の皆様お疲れ様でした〜。
「えっ、そんなのあったの?」
という方は こちらをご覧下さい。
(社)東京
乗用旅客自動車協会の公式ページです。
|
目次
|
・タクシー誕生
・大正時代のタクシー
・昭和のタクシー戦前
|
タクシー誕生
|
『日本に乗用自動車が出現したのは明治33年(1900)5月、大正天皇のご成婚の際、在米邦人の日本人会が米国製の電気自動車を1台献納したのが最初』というも残りますが、タクシーの日が8月5日に制定されているとおり、
『大正元年(1912)8月5日、有楽町・数奇屋橋際に『タクシー自動車株式会社』(長晴登社長・資本金50万円・T型フォード6台)が創設されたのが最初』
もちろん、現在の流し営業ではなく車庫待ち営業でした。
というのが神話のはじまり〜となっています。
この時のタクシーはメーター付き車両で 1マイル、1.6Kmが60銭でした。
(半マイル増すごとに10銭が加算)
因みに山手線は1区間5銭、市電4銭でしたから、かなり高価な乗り物だったわけです。
現代にに換算すると初乗り2千円。以降の加算はほぼ同じ、というところでしょうか…。
ハイヤーとタクシーの違いは後述しますが
、その前にこちらもチェックポイントとして記しておきます。
『トラック運送事業を最初に始めたのは「帝国運輸株式会社」(明治40.12/3開業、代表・渋沢栄一)が経営不振により解散直前の明治43(1910)乗用車2台で「貸し自動車業」ハイヤー業)を始めたのがわが国におけるハイヤー業の始まりである』
|
大正時代のタクシー
|
それは最高の時代でした。
第一次大戦の戦勝景気に沸く中、その真新しさ、もの珍しさから赤坂や新橋の花柳界に出入りする紳士から愛用されました。
さあ、東京に続いて各地にタクシーが登場します。
京都が大正3年に3台、大正4年に5台、大阪は意外に遅く大正5年でした。
営業スタイルは辻待ち。
電話の注文によって出動します。
ほとんどの客は乗車賃の他に多額のチップを渡したから運転者の月収は50円にもなったそうです。
もうちょいと突っ込んで調べましたら、その平均給料は大卒初任給15円時代に25~30円だったといいます。
チップ収入を加えると月収100円を越えていた花形職業でした。
詰衿の上着に乗馬ズボン黒の長靴下に黒の編み上げ靴、皮の帽子という、最新ファッションは映画『俺たちに明日はない』そのままでございます。
…
東旅協のタクシー百年コンテンツに写真があります。
制服の運転者は大モテで、カフェーやバーにはわざわざ制服を着て飲みに出掛けたといいますから
|
|
現代のタクシードライバーとくらべると隔世の感がありますね。
いきおい志望者も増えますが免許合格率は2〜3%という厳しさでした。
それがまた、タクシードライバーの地位を高めました。
|
嗚呼、関東大震災
|
景気の良い時代にスタートし、順調に発展したタクシーでしたが、5年ほどすると不況期に入り、いささか低迷します。
タクシー料金のダンピングが横行するようになりました。
となれば花形職業だったドライバーの資質もレベルダウンしてしまいした。
となれば、盛り返すのには組織力です。
事業者の不況対策から生まれたのが、 それでまでの
車庫待ち営業から、流し営業を
するようになりました。
大正10年のことでした。
そんな最初の10年は
「
人力車を徐々に駆逐して定着」
というところですね。
さて、大正12年のことです。
近年も災害のあるたび、移動体として貢献しているタクシーが最初に注目される歴史的な出来事が起こります。
関東大震災です。
東京の鉄道・路面電車が壊滅しました。
このことにより、それまで副次的に扱われていた自動車が、ついに表舞台に出ます。
自動車輸送は飛躍的発展!
タクシーの世界と申しますと、われも、流入してきますので、
いいタクシーと悪いタクシー
極端な2種類のタクシーが
巷に溢れ混乱したといいます。
結果、初めて天の声が下ります。
タクシー事業が警察許可制となったのです。
そして昭和へと続きます。 つづく。 |
| |
| |
Copyright〈C〉2004. [ U4 project ] All rights received. |